子どもの頃から胸に抱いてきた、将来の夢。
殆どの人間はその夢を手放すか、または忘却の彼方へと追いやる。
夢は叶わない。それはこの世界ではとても当たり前のことで、すごく普通のこと。
だからこそ、優里少年が掴んだチャンスはとても尊い物だった。
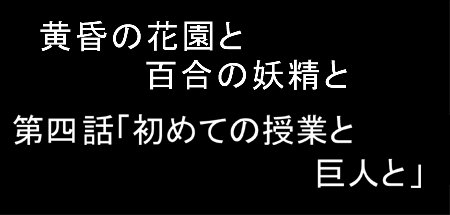
***
四月十一日。日本天蘭学園の入学式から一日経った今日から授業が始まる。
それはユリにとって、とても大切な日。
なん、だけど。
「嘘!? 嘘でしょ!? なんでアラーム鳴ってないの!?」
急に慌しくなる芹葉家。その慌しさの原因は、緊張と興奮で思うように寝られず、それに加え目覚まし時計のアラームをセットし忘れたユリである。
その騒ぎのおかげでユリの祖父である芹葉大吾が、飲んでいたお茶をこぼして火傷しかけるなどといった被害がでたが、まあ別にどうでもいいことだ。
「まったく、もう。二日目で遅刻なんて洒落にならないわよ?」
TVに映るニュース番組を見ながら、美弥子は呆れて呟く。
が、大急ぎで着替えているユリはそんなこと聞いてられない。
「それじゃ、行ってきます!!」
着替え終わったユリは玄関に走り出す。
残念ながら、口に食パンを咥えて走り出すなどといった、お約束な風景は見られなかった。芹葉家は、パンよりお米派だからだ。
そういう問題でも無いか。
「忘れ物は無いか?」
大吾が聞くがユリはもう出て行った後。彼の言葉は寂しく、ユリが数瞬前まで居た玄関に響くだけだった。
「まあ、優里くんもそんな間抜けなことするわけないですよ」
美弥子が笑っているが、それを無視したように大吾は黙って一点を見つめている。
彼女もつられて大吾の視線の先に目を向けると、そこには大吾が優里のために作った弁当が置かれていた。
「「………」」
二人とも黙り込んでしまう。
「……それじゃ、私、二度寝しますんで」
美弥子はいち早く現実へと戻り、いつも通りの生活に送ることにした。
というか、ダメ人間的生活スタイルである。
神凪琴音。『神が作り出した芸術』、なんて二流なお世辞を言われたこともある端正な顔は、何の表情も映し出していない。
彼女は自分の教室である2−Aの窓際の席に座って、外の景色を眺めていた。その光景はどこか憂いを帯び、絵になる。
だが、実は彼女のこの行動は一種の逃避であり、朝の美しい風景を見て、心を潤わそうなんていう素敵な思考が生み出したものでは無かった。
琴音は自分に逃げちゃダメだと言い聞かす。どこか、そのセリフは古いように思える。
彼女はそのセリフを十回ほど心の中で唱えた後、視線を反対側に向け、新しいクラスの面々を見る。
そこには退屈な外の景色を見るはめになった、逃避の原因があると知りながらも。
教室内にはクラス替えをしたために見知らぬ生徒の顔も多い。
まあ琴音は他人に対して興味を持つことなどほとんど無かったためにそんなことは気にしていなかった。
今気になるのは……隣に居る女生徒の集団である。
「……火狩さん?」
琴音はその集団の中にいる一人の少女に話しかけた。
「なんですか琴音さま?」
すぐに返事をして琴音の前に飛んできたこの子は『琴音さまファンクラブ』という組織の一員であったはずだ。
多分一緒に居た子達もファンクラブのメンバーなのだろう。
「確か……あなたも2−Aだったわね?」
「はいそうです!! 一年間よろしくお願いします」
そう言って火狩まことはお辞儀をする。
「そう……同じクラスなのね」
軽い眩暈がしたが、なんとか言葉を紡ぐ。
まあ例えこの子が同じクラスでなかったとしても、ファンクラブのメンバー数からいって、同じクラスにならない確率はものすごく低いものである。宝くじの三等ぐらいの、確率である。
ものすご〜く低いものであるのだが、どうしてもその希望を捨てることは出来なかった。
ちょっとした絶望感に包まれながらも、彼女はまた窓の外の風景を見る。また、逃避したのだ。
「あ……」
「どうかしました?」
琴音が発した声を聞いて、まだ隣に居たまことが尋ねてきた。
「いえ……なんでもないわ」
そうは言っているが何か様子がおかしい。
さっきまでどこか絶望していた表情だったはずの顔に、笑みが浮かんでいる気がする。
「……?」
ふと琴音の視線の先が気になってまことは窓の外を見る。
その目に映ったのは、遅刻ぎりぎりであるために走っている一人の生徒……芹葉ユリの姿だった。
***
「ま、間に合った」
なんとか遅刻は免れ、教室に到着したユリは大きく息をついた。
まだHRは始まってなく、先生も来ていない。
「大丈夫? だいぶ辛そうだけど」
隣の席のアスカが心配してくれる。
「う、うん。ちょっと寝不足ってこともあって……」
走ってきたために体が熱い。じっとりとイヤな汗もかいていた。
身体を冷ますために、制服の首元を引っ張り熱を逃がそうとする。ぱたぱたと空気を循環させると体が冷えてくる。それがなかなか気持ちいい。
「ちょっ!? ユリ!?」
なにやらやけにアスカが慌てている。
「え!? どうしたの?」
「そ、そんなことするんじゃないの!!」
アスカはユリの手を掴み、冷却運動を止めさせる。
「え……!?」
しばらく意味が分からずにいたユリだが、自分の格好を思い出してようやく理解した。
「あ〜……」
なんというか……かなりさっきの行動はチラリズムの大安売りだったような気がする。
鎖骨が見えまくりで、そのフェチじゃなくても堪らないものがあるだろう。
気のせいか近くにいた男子の顔が紅い。ウブだなぁ、なんて的違いなことをユリは考えた。かなり、寝不足で頭に血が行っていないらしい。
「ユリって無防備すぎだよ……」
アスカは呆れている。
「こ、こういう格好はあまり慣れて無くてさ……」
慣れてたまるかと心の中では思っているがそんなこと口に出せない。
「ふ〜ん……もしかしてスカートもあまり穿いたこと無い?」
「そうだけど……わかる?」
「うん、なんか初々しいから」
「へ、へぇ〜……」
やはり、分かってしまうものらしい。
ユリは改めて気を引き締めることを心に誓った。
「皆さんおはよ〜!!」
無駄に明るい声が聞こえて麻衣教諭が教室に入ってくる。
もう一人の教師の姿が見えないがどうかしたのだろうか?
「えっとかおりぴょんは午前中休むそうです……」
彼女に禁止されたはずのあだ名をやすやすと言い放った麻衣教諭は、突然右腕を差し出し親指を立てる。
「実は昨日の飲み会で私がぶっ潰したのである!!」
なんとも誇らしげにそう宣言した。
『なにやってんだこの先生たちは』
1−C全員がそう心の中で叫んだ。
教室の中で、哀を叫んだ。
***
今日の1−Cの時間割では午前中の四時間は一般教養、午後の二時間は技術科、操機手科の授業になっていた。
いきなりT・Gearに乗れるとは思わないが、午後の授業がユリは待ち遠しかった。
その期待感があったためか寝不足であるにも関わらず、黙々と一般教養の授業をこなせていけた。
といっても初めての授業なので、殆どの時間が教師への自己紹介で終わっていたこともあるのだろうが。
午前十一時。一人の初老の男性が天蘭学園の門の前に居た。
ユリの祖父である芹葉大吾である。
彼はユリの忘れていった弁当を届けに来たのだ。
天蘭学園には学食も購買もあるので、ユリのとっては別に支障が無いのだが、せっかく孫のために作った弁当をそのままにしておくのは勿体無い。
天蘭学園の事務局にでも届けようと思い、学園内を歩き出した大吾に声がかけられた。
「もしかして……大吾さん?」
大吾が振り返ると、そこには一人の中年女性が居た。
彼女は学園内にある花壇に花を植えていたらしく、青いつなぎの作業服に、麦わら帽子とスコップという格好だった。
「ああ……佳代子さん」
大吾は思い出したようにその名を呼ぶ。
「あら、覚えててくださったのね」
女性は嬉しそうに微笑んだ。彼女は、どうやら大吾の知り合いらしい。
「こんな所に何の用です?」
「ちょっと知り合いの子に渡す物がありまして……」
自分の孫……とは言わない。そこからユリの存在が推測されるのはまずかった。
「そうですか。それならこの先に事務局がありますので、そこで呼び出してもらったら?」
女性は事務局の方向を指す。
「ええ、わかりました。それでは……」
立ち去ろうとする大吾に再び女性は声をかける。
「大吾さん。用事が終わったらお茶でもしませんか? あなたと話したいことが沢山ありますので……」
「ええ……私は構いませんが」
少し考える仕草をする。
「なにか問題でも?」
大吾は佳代子の姿を見ながら
「……『学園長』というのはそんなに暇なものなのかね?」
と笑って言った。
***
午前中の授業が全て終わり、昼休みになる。生徒たちは皆、思い思いの場所で食事を取る。
教室で食べる者も少なくないが、半分以上の生徒は外へとくりだして行く。
そしてユリたちも外へと食べに行く事になっていた。
「あれ?」
随分と間抜けな声を上げるユリ。理由は知っての通り、弁当を忘れてきたことに、今ごろ気付いたためである。
「あら〜……お弁当忘れちゃったの?」
ユリ達の席にやってきた千秋が言う。
「うん……そうみたい」
溜め息をつきながらユリは自分の財布を取る。
購買にでも行こうと思ったのだろう。
『1−Cの芹葉ユリさん。至急、事務室へおいでください』
「え? ボク?」
突然の放送に驚いたが取り合えず席を立って事務室へ向かうことにする。
「アスカさん達は先に食べてていいよ」
「あ、うん。わかった」
いつ終わるか分からない用事で友人を待たすのは気が引けた。それなら先に食べててもらったほうが、断然気が楽だ。
(一体何なんだろう……?)
ユリは呼び出しの理由をあれこれ考えながら事務室へ歩き出す。
「おじいちゃん……」
事務室に入っていったユリを待っていたのは祖父の大吾であった。
彼は何も言わず弁当の包みを手渡す。
「あ、ごめん。変な手間かけさせて……」
ユリが申し訳なさそうに謝る。
「いや、別にいい。お前が通う学校を見ることが出来たし……昔の友人にも会えたしな」
「友人? おじいちゃん、ここに知り合いがいたの?」
ユリの質問に大吾はまあな、と答えるだけだった。
「あら、これが大吾さんのお知り合いの子?」
事務室のドアの方を見ると中年の女性が立っている。
ユリはこの女性に見覚えがあった。
「え……田上学園長?」
入学式に壇上で挨拶していた時とは着ている物が違いすぎるが、
間違いなく天蘭学園の学園長……田上佳奈子(たうえ かなこ)であった。
田上学園長はユリが驚く様子を気にすることなく近づいて頬を撫でる。
「可愛い子ねぇ。大吾さんとはどういう関係?」
「え、えっと……」
返答に困っているユリを見かねて、大吾が答える。
「私の養子なんだ」
「へぇ、そうだったの……」
問いに答えても、ニコニコしながら撫でるのを止めてくれない。
「あ、あの……」
どうこの場から逃げようかと考えていたところ、
「ユリ、そろそろ教室に戻りなさい」
と大吾が助け舟を出してくれた。
「あ、はい。それじゃ失礼します」
とたとたとユリは走っていった。
逃げていったと言うほうが的確だったかもしれないが。
「あなたのような人が養子を取るなんて思わなかったわ」
学園長はしみじみと呟く。
「そんなに以外だったかね?」
「ええ、あなたはとっても無愛想だから。奥さん以外の方が、あなたに懐くとは思えなかったもの」
かなり、酷いことを言われているのだが、結構大吾の本質を表している。
笑っている彼女に、大吾は何も言うことは出来なかった。
***
ユリは弁当を受け取ると教室に戻ろうとしたのだが、ふと昨日アスカを探している時に発見した植物園のことを思い出した。
(あそこでご飯食べると気持ち良いだろうなぁ……)
思ったら吉日。すぐにそこに向かうことにする。
弁当を食べやすい場所であったならば、明日にでもアスカたちを誘えばいいと考えていた。
ちょうど先に食べていてと言ったばかりなのだし。
生徒用玄関で靴に履き替え、校舎を出た先に広がる演習場の反対側に歩き出す。
T・Gearの格納庫や、その他のよく分からない建造物の合間を縫って進むとその場所が見えてきた。
昨日と何一つ変わらない、木の葉の奏でる音が聞こえてくる。
ユリがこの場所を植物園と名称した通り、様々な種類の木々が彼女の目の前に広がっていた。
人工芝でない緑の地面がとても美しい。
ここで寝転んで空を見上げれば小さな悩みなど消えてなくなる気がする。
(もしかしたら昨日会った先輩もそんな気分だったのかな?)
昨日起きた出来事を思い出しながら、奥へと進んでいく。
「あら……」
上品そうな声が緑の空間に響いた。
「え!?」
声の聞こえた場所には一人の女性が座っていた。昨日と同じ人間が、同じ場所で。
昨日と違うのは彼女は死体のマネ……でははく、寝てはなく、傍らに弁当箱を置いていた所だけだろう。
「あ、昨日はどうも……」
ユリは驚きつつもお辞儀する。
「あなたもここに食事しに?」
「え、あ、はい。ここで食べたら気持ちいいだろうと思いまして……」
目の前の女性の上品な言葉遣いに引きずられて、ユリの言葉が変になっている気がする。
そのことに気付いたのか女性は少し笑っていた。
「そんなに緊張しなくてもいいわよ……」
「す、すみません」
自分の行動が読み取られているみたいで恥ずかしく、ユリは俯いてしまう。
「えっと、それじゃ、邪魔しちゃったみたいなので……」
ユリは再びお辞儀し、立ち去ろうとする。
「良かったらご一緒にどう?」
「え!?」
思いがけない言葉にまたもや驚くユリ。
「で、でも……」
「そう……嫌なのね」
女性は俯き加減にそう言う。
「いいえ、とんでもないです!!」
誰が、彼女のそんな表情を見て、断ることが出来るだろうか。
ユリは何故か心の中で、そう言い訳した。
***
やはり新入生としての立場のせいか、ユリは緊張していた。目線をどこに向けていいか悩んでいる。
上級生と二人きりで食事するのは、同年代の子とのそれとは違うのだろう。10代の若者にとって一年の差は、とても大きいのだ。
そのぎこちなさがユリの目の前にいる彼女も気付いたのか、やさしく話しかけてくる。
「そう言えば、まだ名前を聞いていなかったわね。
私の名前は神凪琴音。二年生よ」
「ふぁ?」
口いっぱいにご飯を詰め込んでいたユリは、とても気の抜けた声をあげた。多分、驚きの声だったのだろう。
「んぐんぐ……えっと、ボクの名前は芹葉ユリです」
そう言い終わると、琴音はユリに手を差し出してきた。
「よろしくね芹葉さん」
「はい、こちらこそ神凪さん」
琴音の細く綺麗な手を握りながら、なにが『よろしく』なのだろうとユリは考える。
仲良くしよう、ということなのだろうか?
考えてもよく分からないため、とりあえずまた目の前のお弁当を片付けることにした。
神凪琴音、という人間から見て、芹葉ユリと名乗った少女は、何とも可愛らしく見えた。
目の前の上級生に気を使い、どこかビクビクしてる彼女は、どこか保護欲を誘うものがある。
そのまま緊張しているままで居させるのは、せっかくの昼食を不味くさせるだけなので、話しかけてあげることにする。
「そう言えば、まだ名前を聞いていなかったわね。
私の名前は神凪琴音。二年生よ」
「ふぁ?」
今流行の挨拶なのかと思ったが、そんなわけは無い。驚いて、うまく声を出せなかったのだろう。
そんな所も、何だか愛らしく思えた。
「んぐんぐ……えっと、ボクの名前は芹葉ユリです」
「よろしくね芹葉さん」
琴音はユリに手を差し出す。
『よろしく』という言葉が自然に出たのは、自分自身でも何故だか不思議だった。
「はい、こちらこそ神凪さん」
ユリがそう返してくる。
琴音は苗字で呼ばれたことに、少しばかり心に引っかかりを覚えた。彼女は、神凪、という苗字は嫌いだった。
「名前の方で呼んでくださらない? 苗字で呼ばれるのは嫌いなの」
「え!? わ、わかりました。それじゃボクも名前でお願いします」
照れているユリの表情が可愛い。
彼女から許可を貰ったのだから、早速名前で呼んでみることにする。
「ユリ?」
「ふぇ!? な、なんですか琴音さん?」
(『様』を付けられずに呼ばれたのは久しぶりだわね……)
そんなことを心のなかで思いながらユリの頬へ手を伸ばす。
「ご飯粒がついてますわよ」
ユリの頬に付いていたご飯粒を取ってあげ、自分の口に運ぶ。
「な!? なぁ!!??」
ユリは驚いたようで顔を紅くして変な声を出している。
そんな表情を見るのが、琴音は面白くて仕方なかった。先ほど感じていた保護欲が、実は嗜虐欲であったと気付くのに、時間はかからなかった。
***
ユリの視点から見た神凪琴音という人物は、アスカや千秋から聞いた人物像とは違っていたように思える。
確かにお嬢様で容姿端麗というのは聞いたとおりだったが、厳しいだの冷たいだの鬼なのだとかいう感じは受けなかった。
っていうかさすがにそれは言い過ぎだ。
そんな風評とはまったく違い、後輩の面倒を良く見てくれるいい先輩のように見える。
表情も良く変わり、鉄仮面だとか言われているのが不思議な、普通の少女と言ってもいいのではないかと思う。
というか、鉄仮面という二つ名をつけるのは、いささか失礼だろうに。
「ふう……ご馳走様」
ユリは大吾の持ってきてくれた弁当を食べ終えた。
もうすでに食べ終えていた琴音に視線を移すと、彼女もユリを見ていたらしく目があった。
すこし恥ずかしかったが、気にしないように質問する。
「琴音さんはよくここで昼食を食べるんですか?」
「いつもって訳じゃないけど、よく来るわね」
「へぇ〜……」
(話が終わってしまった……)
見知らぬ他人とのこのような沈黙は辛い以外のなんでもないのだが、琴音はそんなこと気にせず、柔らかな笑みを浮かべてユリを見ている。
ユリは何か笑われるようなことしたのかと思い、自分の姿を確認したりしてみるが、別におかしい所は無かった。
「……どうして笑ってるんですか?」
思い切って聞いてみた。
すると琴音はその質問の意味がよく分かっていないのか聞き返してくる。
「私……笑っていた?」
「はい……ボクのほう見て」
そうだったの……と考えている琴音。どうやら意識していた訳じゃなかったらしい。無意識に笑われるのも、なんか嫌だと思うけど。
しばらく何かを考えている表情をしていた琴音が口を開いた。質問の答えがどうやら見つかったらしい。
「きっと……ユリが可愛かったからね」
そう言って綺麗な笑みをユリに向けてきた。答えを聞いたユリは対照的に顔を引きつらせていたが。
「へ、へぇ〜……ボクハカワイインダァ」
なんていうか、すごく凹んだ。
***
昼休みが終わるまで後十分足らず。
要領のいい者は次の授業の準備やお手洗いを済ませ、そんなの関係無いとしている者は友達とまだ喋り通している。
少しそんな生徒たちとは違う動きをしている者もいた。
『琴音さまファンクラブ』の会員番号1084、火狩まことであった。
ちなみに天蘭学園の生徒数は約450名ほどである。
全生徒がファンクラブの会員になったとしても会員番号が三桁を超えるはずはない。
つまり『琴音さまファンクラブ』は学園外にまでその勢力を伸ばしているということになる。琴音が頭を抱えるのも無理はない規模だ。
下手なアイドルよりもてはやされている今の状況は、世界を救う英雄候補としての全人類の期待があるのだろう。
多分。
火狩まことは昼休みになると同時に姿を消した琴音を探していた。
四時間目の授業の終了と同時に彼女の席に向かったのだが、席に残されていたのは琴音の温もりだけで、彼女の姿はそこには無かった。
日々ファンクラブから逃げるのが上手くなってきているのは気のせいでは無いと思う。
「もう〜、琴音さまどこにいるのぉ……」
琴音に憧れて伸ばし始めた髪をいじりながら呟く。
他のファンクラブメンバーも彼女を探しているが、出来ることなら自分が一番先に見つけ出したい。
ファンクラブのメンバーといえどある意味ではライバルなのだ。
「あ!! 居た!!」
ついに琴音の姿を瞳に捉えることが出来たらしい。
彼女は全速力でその場所に向かっていこうとするが、すぐに足を止める。
(え……!? あの子だれ?)
まことの視線の先には校舎へと向かってくる琴音と、芹葉ユリの姿があった。
***
2−Aの五時間目の授業風景が広がっている。
二年生となると教師の顔は大体知っているので自己紹介うんぬんは飛ばされて授業をやっている。
生徒たちは文句を言っていたが、一年次の授業の復習であるからという理由で納得してもらっていた。
「……」
火狩まことは授業のプリントに手をつけることなく少し離れた琴音の姿を見ていた。
琴音のことだから、すでにプリントの問題は解いてしまったのだろう。
窓際の席に座っていた琴音は、いつもと同じ様に外の風景を眺めていた。
(あんな風に笑っていた琴音さま……初めて見た)
まことの目は授業中の琴音を映していながらも、頭の中には昼休みの笑顔が頭に浮かぶ。
その笑顔は隣にいた少女によってもたらされた物であるのは、遠目からでもすぐにわかった。
そしてその少女が一流のコメディアンで、ものすごく面白いジョークで琴音を笑わしている、ということなら何も言うことは無いのだけど。
多分、というか絶対違うだろう。
(あの子誰だったんだろう?)
初めはファンクラブの子かと思ったが見覚えが無かった。
スカーフの色から一年生であることが分かったが、それ以上の有力な情報は何も得られていない。
まあ、どこの誰であろうとまことが彼女に抱く感情は一つだったわけだが……。
(……すごくむかつく)
こうして芹葉ユリは入学早々であるのに、一人の敵を生み出していた。
多分、ユリに非は無いと思うけど。
「これから授業を始めます」
香織教諭の声が響き、校舎から遠く離れた演習場で1−Cの五時間目の授業が始まる。
演習場は草木が少なく荒れ果てた大地であった。
そこに白を基調としたシンプルな造型のT・Gearが三体立っている。
荒野に鋼の巨人がそびえ立っているのはどこか畏怖すら感じさせる光景であった。
生徒たちは、そんななんとも言えぬ場所に立たされ、どこか落ち着かない雰囲気だった。
ちなみに生徒は全員天蘭学園特注のジャージを着用。
なんでもT・Gearの実習は毎回これを着るらしい。
「えっとまず、これからの授業の形についてだけど……」
心なしか顔色の悪い香織教諭が、目の前にいる生徒たちに向けて話を始める。
ちなみに今日の授業は技術科と操機手科、両方の生徒たちが受けることになっているらしい。
話が始まると、麻衣教諭はつまらなさそうに用意してあった数体のT・Gearを起動させ始めた。
「T・Gearについての授業は技術科、操機手科共通の講義。
二つに分かれる実習があります。
講義では主にT・Gearの基礎的な知識を学びます」
麻衣教諭は起動させていたT・Gearのコックピットから、顔を出して叫ぶ。
「パイロットなのに機体のこと全然知らないのは生死にかかわるからぁ!!
かおりぴょんの講義は眠たくて辛いだろうけど頑張ってぇ!!」
彼女の言葉に思わず生徒たちは笑ってしまう。
「うるさい!! 頭に響くから大声は止めなさい!!」
どうやら香織教諭はまだ体調が回復したわけでは無いらしい。
「実習では操機手科はT・Gearの操縦訓練。
技術科は共通講義とは違う内容の授業と実際の整備。
ただし技術科は、二年次に機体開発のハードウェア部門と、
火器管制システムやオートバランスシステムなどのソフトウェア部門に別れますのでそのつもりで」
頭をおさえつつ香織教諭は一気に説明する。
説明が終わったのを待っていたのか麻衣教諭が声を上げる。
「は〜い!! みんな注目〜!!」
妙に古い学園ドラマを思い浮かべそうなセリフだ。
彼女はまだコックピットに居た。
「この子が今からあなた達を育ててくれるT・Gearです。
さすがにG・Gで配備されているやつとは見劣りするけど、愛情持って接してあげてね」
なんとも彼女らしい説明の仕方だ。
「機種名は『Acer』よ。
もとから練習機として開発されたものだから整備、及び操作が簡単なの。
T・Gearの基礎を学ぶのには持って来いの機体よ」
後から香織教諭が正確な説明をする。
なんだかんだでこの二人は息があってるのだろう。
ちなみに説明の間……ユリは目を輝かせながらずっとAcerを見ていた。
「すごい……もう泣きそう」
「だ、大丈夫?」
隣に居たアスカが心配そうに声をかける。
だがその事にもユリは気付いてないらしい。
「何度この光景を夢に見たことか……うっ、ううっ」
っていうか本当に泣き出した。
さすがにこれには友人も引く。
「そんなに感動しなくても……」
その言葉を聞き、急にユリはアスカの方を向く。
「アスカさんは何も感じないの!?
これからボクたちはパイロットになるための訓練を受けられるんだよ!?」
今まで見たことのない強い目をしたユリが迫ってくる。
(す、すごい一生懸命……)
アスカはさすがにこの変貌には驚いた。
今まで周りに流されることの多かったはずのユリが、こうも自分の意思を人に向けてくるとは……。
(人間って分からないわね……)
目の前で熱く語りだしたユリを見ながらアスカはそう呟いた。
***
「よし、取り合えず乗ってもらいましょ!!」
麻衣教諭はいつもの明るい声で生徒たちに言う。
「ちょっと!? いきなりそれは無理でしょ!?」
香織教諭が辛そうに叫ぶ。そんなに昨日は飲んだのだろうか?
「習うより慣れろってね。
下手な講義を受けて妙な先入観を抱かれるより、
さっさと本当のT・Gearがどういうものか体で分かってもらいましょうよ」
香織教諭の反撃をもっともらしく聞こえる理屈でかわす。どこか慣れているように感じるのは気のせいではないはず。
「それじゃ乗りたい人は〜?」
麻衣教諭の声に一番早く反応したのはもちろんユリだった。
「はい!! ボクが乗りたいです!!」
あんなに目立つことを嫌っていたくせに、こういうことには羞恥心だとかそういう物が欠落してしまうらしい。
「お!! いい心意気だねぇ。それじゃ、せ……そこのあなた!!」
どうやら名前を言おうとしたが憶えていなかったらしい。何のための昨日の自己紹介だったのか。
とにかく麻衣はユリを指名した。
「さ、こっちに来なさい」
「はい!!」
緊張してるのか興奮してるのか知らないが、やけに危なげな足取りでAcerに向かっていくユリ。
それをクラスメイトは固唾の呑んで見守っている。
ユリは巨人の足元までくると、備え付けられていたタラップでコックピットへ昇っていく。
「さ、こっちに座りなさい」
麻衣教諭は昇りきったユリを座席へ招く。
ガチャ、ガチャ―――ベルトをユリの腰、肩にそれぞれ装着する。
「これでよし、と。それじゃね」
そう言うとさっそうと降りていく麻衣教諭。
「え!? 操縦方法とか何か教えてくれないんですか!?」
降りていく途中だった麻衣教諭は振り返ると笑みを浮かべ
「根性よ!!」
と励ましてくれた。
「根性でどうにかなっちゃうんですか!?」
ユリのまともなツッコミは暴走教師に届かなかったのか、タラップを機体から外されコックピットが閉められる。
「あ、あの!! ちょっと!?」
ユリの目の前には数々の見知らぬ計器と巨人の視界を映すディスプレイがある。知識も無いのにどう動かせばいいといのだろうか。
(あの先生……やっぱり無茶苦茶だよぉ)
『もしも〜し、聞こえてる?』
「は、はいぃ!!」
横にあったスピーカーから麻衣の声が聞こえる。
彼女に対して良からぬ想いを抱いていたのを読まれたのかと慌ててしまう。
『一応他の生徒の見本にしなくちゃいけないから、私が動いてって言ったら動きだしてね?』
「は、はい。分かりました」
『それとね』
「なんですか?」
『……気をつけて』
「……は、はい」
ユリは今まで聞いたことの無い優しさのこもった声を聞いて、胸いっぱいだった喜びが薄れ……不安で満たされてしまった。
***
「ユリ……」
アスカは先ほど巨人の中へと消えてしまった友人の名前を呟いた。
彼女たち1−Cの生徒たちは先ほど二人の教師によってT・Gearから遠ざけられている。
「さて!! それでは皆注目して〜」
能天気な教師が大声をあげる。
アスカの麻衣教諭への印象はあまりいいものではない。そのためか少し彼女を見る目がきつくなっている。
「さあ、ユリちゃん!! 思う存分暴れちゃいなさい!!」
おそらくもう一人の教師からユリの名前を聞いたのであろう。ユリの名前を呼ぶ。
それにしても、何とふざけたGOサインなのか。
やはりこの発言を聞いて、アスカの視線はよりきついものになる。
『は、は〜い。分かりました』
スピーカーで増幅されたユリの声があたりに響く。
するとゆっくりとだがユリが乗ったT・Gear……Acerが動き出した。
右足が上がり歩み出そうとする。
「動いた……」
「すごい……」
生徒たちの間から驚きの声が上がる。
「ユリ……」
もう一度アスカは友人の名を呼ぶ。
彼女は……ユリは今こうしてT・Gearのパイロットとしての一歩を踏み出したのだった。
……踏み出した様に見えた。
『うわあぁぁ!!!!』
という大声と
『ズドオオオン!!』
という地響きが演習場に鳴り響く。
辺りには砂塵が舞い散り生徒たちの視界を奪う。
生徒たちは皆咳き込み、一体何が起きたのか分からず軽いパニックに陥った。
「落ち着きなさい!!」
妙なあだ名を持つ教師が生徒たちを落ち着かせる。
砂塵が落ち着いて視界が見えるようになるとようやく状況が分かってきた。
生徒たちの前に広がっていたのは、ものすごく間抜けな格好で地面に突っ込んでいるAcerであった。
「……」
そのシュールな光景に、場が静まり返る。
そして当然という顔をした麻衣教諭が言った。
「まあ、何も知らずに歩けたら苦労しないわよね」
(((この教師は悪魔だ)))
入学二日目だというのにやけに心の声がシンクロする1−Cは
思わず皆笑いだしてしまった。
「うう……酷いぃ」
思い切り被害者であるユリは
乗り込むことが夢であったはずのコックピットで涙を流していたのだった。
合掌。
第四話「初めての授業と巨人と」 完
目次へ 第五話へ